 |
<講 演> 「バッハゆかりの都市を訪ねて」 松本 彰(新潟大学人文学部 教授) <演奏曲目> 前奏曲とフーガ イ短調 BWV543 オルガン独奏:市川純子 《シュープラー・コラール集》より 「目覚めよ,とわれらに呼ばわる物見らの声」BWV645 オルガン独奏:大作 綾 《17のコラール》より 「いと高きところには神にのみ栄光あれ」BWV663 オルガン独奏:海津 淳 「来ませ,造り主なる聖霊の神よ」BWV667 オルガン独奏:大作 綾 パッサカリアとフーガ ハ短調 BWV582 オルガン独奏:渡辺まゆみ |
|
バッハゆかりの都市を訪ねて
松本 彰 |
|
| バッハが生涯を過ごしたのは,右図に示すようにドイツ中部のごく狭い地域です.幼くして両親を亡くした彼は,音楽家として活躍していたバッハ家一族の人々に助けられ,この地方の諸都市を渡り歩くなかで音楽家として成長していきました.昨年夏,新潟オルガン研究会の仲間とそれらの都市を訪ねました.それぞれ個性的で魅力あるドイツの地方都市の姿をスライドで紹介しながら,バッハの生涯と音楽について考えます. 1.アイゼナッハ 2.オールドルフ 3.リューネブルク 4.ヴァイマル 5.アルンシュタット 6.ミュールハウゼン 7.ヴァイマル 8.ケーテン 9.ライプツィヒ |
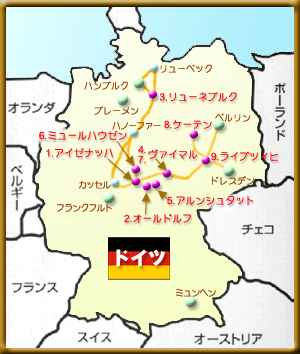 |
| 【バッハの居住地】 | ||
| 都市名 | 期間(年齢) | 職務など |
|---|---|---|
| アイゼナッハ | 1685.3-1695(0-10歳) | 1693頃からラテン語学校生 |
| オールドルフ | 1695-1700(10-15歳) | 高等中学校生 |
| リューネブルク | 1700-1702(10-17歳) | 聖ミカエル教会附属学校生 |
| ヴァイマル | 1703.3-1703.8(18歳) | ザクセン=ヴァイマル公宮廷楽師兼従僕 |
| アルンシュタット | 1703.8-1707.6(18-22歳) | 新教会オルガニスト |
| ミュールハウゼン | 1707.6-1708.6(22-23歳) | 聖ブラジウス教会オルガニスト |
| ヴァイマル | 1708.7-1717.12(23-32歳) | ザクセン=ヴァイマル公宮廷オルガニスト兼宮廷音楽家,宮廷楽師長(1714.3) |
| ケーテン | 1717.12-1723.4 (32-38歳) | アンハルト=ケーテン候宮廷楽長 |
| ライプツィヒ | 1723.5-1750.7(38-65歳) | ライプツィヒ市音楽監督兼聖トマス教会カントル,ザクセン選帝候宮廷作曲家(1736.11) |
| 【曲目解説】 J.S.バッハ(J.S. Bach, 1685-1750) 前奏曲とフーガ イ短調 BWV543 この作品の初稿は,前奏曲がヴァイマル時代に,フーガがケーテン時代に成立したと考えられる.最終稿はライプツィヒ時代の1730年頃になってようやく成立した.前奏曲は比較的短いが,不協和音と半音階的な音型が,きわめて表情豊かな仕上がりをみせている.フーガはチェンバロ用フーガBWV944を改訂したもの.雄大で元気がよい主題と長い間奏部が特徴.終結部では印象的かつドラマチックに展開する.(市川純子) 《シュープラー・コラール集》より 「目覚めよ,とわれらに呼ばわる物見らの声」BWV645 1731年に作曲された同名の教会カンタータBWV140から編曲されたもの.定旋律はテノール(左手)で奏でられる.Ph.ニコライによるコラール(1599)の歌詞は「シオンは物見らが歌うのを聞く/シオンは喜びに心おどる/シオンは目覚めて花婿を迎えるために急ぎ立ちあがる・・・」.真夜中に物見らの声を先導として到着したキリストが,待ちこがれる魂との喜ばしい婚姻へと至る情景を描いている.(大作 綾) 《17のコラール》より 「いと高きところには神にのみ栄光あれ」BWV663 バッハのコラールに基づくオルガン音楽にはいくつかのタイプがあるが,“2つの鍵盤とペダルで/定旋律をテノールに”と冒頭に付記されたこの作品には,明らかな室内楽的性格をみることができる.常に快活で対位法的な2つの上声部とペダルによるバス声部の動きは,バロック期の代表的な室内楽形式トリオ・ソナタそのもの.“2つめの鍵盤”に現れる装飾豊かなコラールの旋律は,甘やかな―たとえばオーボエのような独奏管楽器を思わせる.定旋律としてテノール声部におかれたこのコラールの装飾的・独奏的性格は,もうひとつの典型的書法であるペダル定旋律の力強さとは対照的である.オルガンのもつ複数の鍵盤と多様な音色が生彩を放つ作品である.(海津 淳) 「来ませ,創り主なる聖霊の神よ」BWV667 《17のコラール》は,バッハが若い頃作曲したコラールを晩年になって改訂・補筆した曲からなり,バッハのオルガンコラール技法の総決算と見なされている.BWV667も<オルガン小曲集>の同名の曲BWV631を1747年頃に拡大したもの.M.ルター作詩(1524)の「聖霊降臨祭」のコラール(1529)が用いられている.初稿部と拡大部の2部構成になっており,コラールの定旋律は,前半はソプラノに,後半はバス(ペダル)に現れる.(大作 綾) パッサカリアとフーガ ハ短調 BWV582 パッサカリアとは変奏曲の一種で,主として短調の3拍子,低音で反復されるオスティナート主題をもつ.この形式によるバッハの作品はこの曲だけ.ヴァイマル時代後期もしくはケーテン時代初期の作と思われる.曲は低音主題が20回くり返されるパッサカリアと,その主題前半にもとづくフーガからなる.まずペダルソロで荘重に始まり,次々にいろいろな声部に主題が移りながら変奏が進む.そして5声部から成る第20変奏の終止和音のC音がそのままフーガの開始音を兼ねる.フーガ主題には,スタカートによる8分音符の鋭い動機(第1対主題)と,16分音符のさざ波のような動機(第2対主題)が伴う.主題と2つの対主題の3つがひとつの大きな流れとなって,徐々に高揚しながら滝のような最終和音へと向かう.(渡辺まゆみ) |